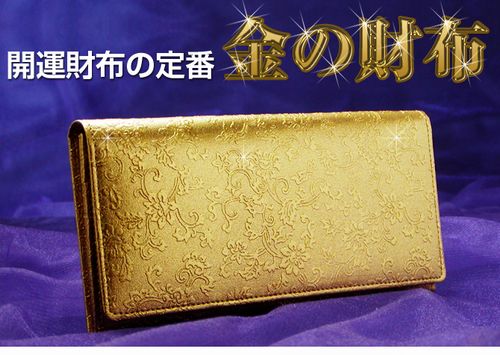こんばんは、智道です。
幸せの貯まる財布![]() の話です。
の話です。
春財布にこんな話があります。
春の訪れを知らせるのに桜の開花が一般的ですが、
その昔の農村では、
”山の神が里に降りてきて田の神様となり、
田の神が桜の木に宿るときに桜が咲く”
と伝えられていました。
満開の桜の下で宴を囲む、
今でいう花見は農村の正式な御神事だったのですね。
桜の芽は開花する前にパンパンに張って一気に開花しますが、
春財布もそれにあやかっているのかもしれません。
春と張るを掛けた和歌もいくつかあります。
●あづさ弓 春たちしより 年月の 射るがごとく 思ほゆるかな
●霞立ち 木の芽もはるの 雪ふれば 花なきさとも 花ぞ散りける
●四方山に 木の芽張る雨 降りぬれば 父母とや 花の頼まむ
●津の国の 難波の葦の 芽もはるに しげき我が恋 人知るらめや
和歌にうたわれたのが、張ると春が掛け合わされた起源となったようです。
現代では春と張るを掛け合わせた言葉で、
春に向かって木の芽が張る状態を、財布がお金で張った状態に例えて
「春財布」と言うのが語源のようですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
おやすみなさい、素敵な夢を(∩^o^)⊃━☆゚.*・。゚

人気ブログランキングに参加しています。
皆さまに幸せと豊かさをお届けするブログを目指してます。
ワンクリックで応援をいただければ励みになります。
↓↓↓